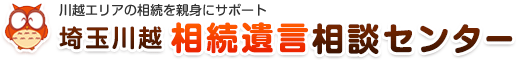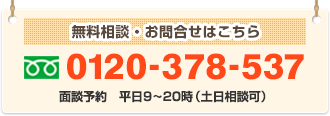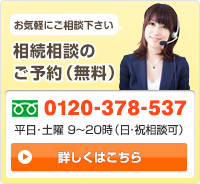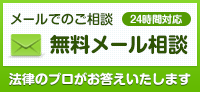法定相続のよくある質問
法定相続の際によくある質問と、その回答を簡単にまとめましたので、どうぞご参考になさってください。
Q.養子は相続人になりますか?
A.実子と同じく、養子も相続人となります。
養子は、実の両親と、養親の財産の両方を相続できます。
ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続することになっています。
また、本当に養子となっているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。戸籍に記載が無ければ、相続人として認められないからです。
Q.前妻または前夫は相続人になりますか?
A.いいえ、相続人にはなりません。
亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが、相続人となります。
Q.前妻または前夫の子供は相続人になりますか?
A.亡くなった人の実の子供は相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は、相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。
ただし、1つ例外があります。連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認をする事が必要となります。
Q.相続人の1人がすでに亡くなっている場合の相続は?
A.この場合、2通り考えられます。
1つは、相続人の亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前なら、
その相続人の子供が全員相続人となります。これを代襲相続といいます。
もう1つは、相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後の場合です。この場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。
Q.相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか?
A.相続人には変わりありませんので、行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。
まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。
もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので、注意しましょう。また、その行方不明者が後から現れて相続権を主張してくると、相続のすべてが一からやり直しとなってしまいます。
こういった行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から、行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。
お気軽にお問合せください。
相続と遺言のご相談お手続は鶴ヶ島駅西口前徒歩1分
埼玉・川越相続遺言相談センター
平日・土曜日は朝9時から夜8時まで受付 日曜・祝日・夜8時以降は予約制です

相続のことは埼玉川越相続遺言相談センターにお任せください!
 |
相続と遺言のご相談とお手続きは鶴ヶ島駅西口前徒歩1分 埼玉・川越相続遺言相談センター 行政書士による無料相談実施中! お気軽にご相談下さい!   |